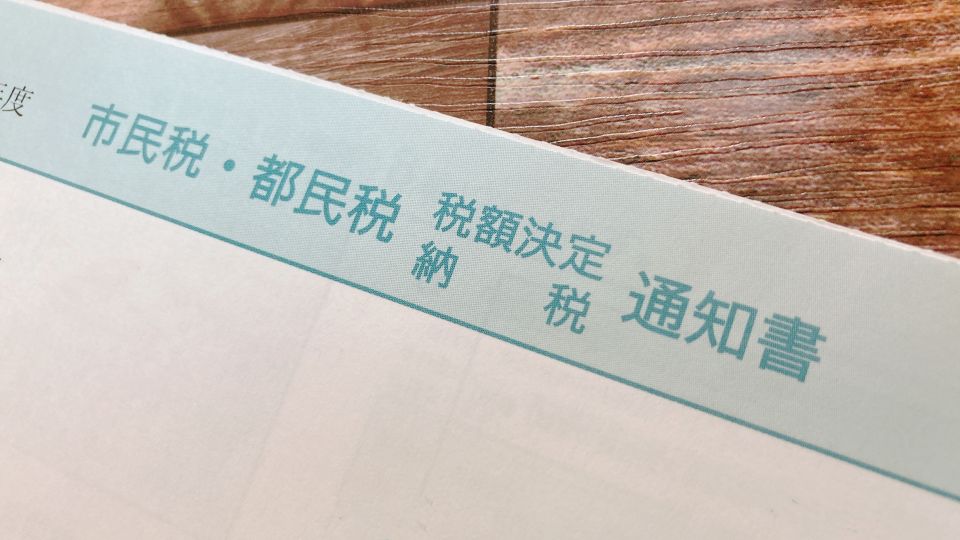会社勤めの方などは給料から天引きで引かれている住民税ですが、自営業やフリーランス、パートやアルバイトの方でも一定以上の所得があれば住民税を納める必要があります。
天引きなどで納める住民税は特別徴収と言って年税額を12等分して毎月引かれるのですが、天引き以外での住民税の納付は普通徴収と言って年税額を4等分した額を6・8・10・1月に納めるか、6月に1年分を一括で納めるかになります。12等分と4等分とではトータルで納める金額は同じだとしても、1回あたりの納付額が多くなる普通徴収のほうが厳しく思えますよね。
住民税って減免で納める金額を抑えることができるのでしょうか、また4等分での支払いを特別徴収のように12等分などに変更できるものなのでしょうか。住民税が払えないピンチを救っていきます。
納税の減免や納税緩和制度もある。
住民税ってなに?
住民税とは1月1日現在で住民登録をしている住民に対して都道府県と市区町村が課税する税金です。都道府県・市区町村ごとに非課税の対象でなければ一律で課税される均等割と、所得に応じて納税額が変わる所得割があり、都道府県と市区町村に納める税金を一括りにして一般的に住民税と呼んでいます。
住民税は前年1月から12月までの所得に対して課税される税金です。
課税されるのは実際に収入のあった翌年の6月以降になるので、いざ税金を納めるときになって収入が激減したり、災害などによって住民税を納めることが難しいということも当然あります。会社を退職して退職金が入り喜んでいると、翌年の6月ごろに市区町村から多額の住民税を納めるようにとの通知が来て慌てることもあります。
お金がないからと住民税を納めずに放置していると本当に大変なことになりますよ。
住民税の減免について
前年の収入・所得に対して課税されて翌年納めることになる住民税ですが、さまざまな事情により今はお金が無くて納められない!というケースは珍しくありません。
そこで住民税を免除や減額してほしい場合、各市区町村に必要な書類を添付して減免申請をすることで住民税を免除または減額してもらえることがあります。
申請しなければそもそも減免は受けられませんが、申請したからと言って必ず減免が受けられるものでもないのです。
実は住民税の減免については各市区町村ともに積極的ではなく(市区町村の収入が減るのですから)こちらから申請方法や必要な添付書類を問い合わせるなどしなければ教えてもらえないことがほとんどです。どこの役所でもそうですが、お金を納めなきゃいけないときは積極的でどんどん納付書を送り付けてきますが、減免だったり補助が出るケースなどはこちらからたずねないと教えてくれないですよね。
また減免の対象者や基準は市区町村によってかなりばらつきがあります。火災や地震などの災害によって被害に合った方のほか、前年に比べて所得(所得の制限アリ)が半分以下に減少などが主な対象となっています。
住民税って分割で払えるの?
住民税の普通徴収は一括納付または4回の分割での納付であることは最初に書きましたが、10万円の住民税を給与天引きで特別徴収ならば12回の分割ですから約9000円と比較的楽なのですよね。
ところが普通徴収となると4回の分割でも25000円ずつと正直言ってかなりイタい。そこで4回の分割を特別徴収並みに12回にしてもらうことは可能なのでしょうか。正規の回数以上で税金を納めることを分納と言いますが、これは比較的簡単に認めてくれるのです。
じつはこの分納は市区町村役場との約束ではなく、あくまで担当した職員との口約束程度ということが多い。
たまにテレビのドキュメンタリーで、市区町村の職員が地方税を滞納した人の家に行き家宅捜索を行い、滞納している地方税を分納で納めさせる口約束をするというシーンを見たことがある方もいらっしゃると思いますが、あのシーンとほぼ同じなんです。
本来は一括だったり定められた回数で納めなきゃいけないのですが、仕方がないから分納は認めますよ。
ただし既定の延滞金はいただきますし、本来の払い方じゃないから督促状は届きますし、納付誓約書にはサインをしてもらいますよ、ってことなのです。
また正規の取り扱いではないために、分納を認めた職員が異動して新しい担当者に変わったとたんにいきなり差し押さえられる、というメチャクチャ怖いケースもあるそうです。
期日までに納められなければ差し押さえますって書かれた納付誓約書にあなたがサインしていますからね……。
ちなみに延滞金(2025年9月現在)は納期限の翌日から2か月間を経過するまでは2.4%、2か月を経過した日以降は8.7%の延滞金が加算されます。
納税緩和制度
先ほどの項で説明した住民税の分割払い(分納)は担当職員とのいわば口約束によるものでしたが、正式な制度として“納税緩和制度”があります。
この制度は法律によって定められたものですので、担当の職員が変わった場合でも急に一括で納めるように迫られたり、いきなり差し押さえられるといったこともありません。
徴収の猶予
次のいずれかに該当する方
- 財産について災害を受けたこと、または盗難にあった
- 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかった、または負傷した
- 事業を廃止したこと、または休止した
- 事業について著しい損失を受けた
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した
認められると原則1年間
- 市税の納税が猶予または財産状況などに応じて分割して納付
- 猶予期間中の延滞金は全部または一部が免除
徴収猶予申請書・財産目録・災害などの事実を証する書類(罹災証明書、医療費の領収書など)のほか、担保が必要な場合には担保提供書などの提出も必要となります。
換価の猶予
換価の猶予とは、すでに差押えされている財産または今後差押え対象となる財産の換価(公売=差押えた財産を換金するために売却すること)を、一定の要件に該当した場合には猶予して税金の分納を認めるという制度です。
市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある恐れがあると認められた場合に適用されます。
- 納税が猶予され市税を分割して納付
- 財産の換価(公売)の猶予
- 猶予期間中(最長1年)の延滞金の全部または一部が免除
換価猶予申請書・財産目録・担保提供書 (担保の提供が必要な場合)などを市区町村に提出します。
担保についてですが名古屋市では
- 猶予を受ける金額が100万円以下
- 猶予を受ける期間が3か月以内
- 担保として提供することができる財産がないなど特別な事情
の場合には担保は必要ないとしています。
また担保となる財産は名古屋市によると
- 国債や市税事務所長が確実と認める上場株式などの有価証券
- 土地、保険を付した建物
- 市税事務所長が確実と認める保証人の保証
となっています。
「徴収の猶予」も「換価の猶予」もともに正式な取り扱いですし、全国どこの市区町村であっても申請書類などの受け取りは拒否できませんから、安易な口約束による分納ではなく納税緩和制度を積極的に利用していきましょう。
まずはお住まいの市区町村役場に相談を
さまざまな理由によって住民税が支払えなくなることは誰にでも起きうることです。
ただ言えることは、支払えないからといって何もせず放置していてはいけません。最終的には差押えなどの強制執行処分につながる可能性が非常に高いからです。まずはお住まいの市区町村役場で事情を話すなど相談してください。
支払いたいのだが今はお金が無くて難しいが、絶対に払いますから今は助けてほしい!こういう態度で役所に臨めば、役所側だって何らかの助け舟は出してくれますから。